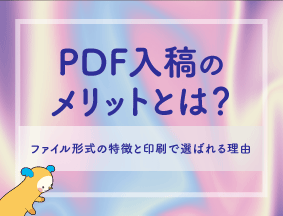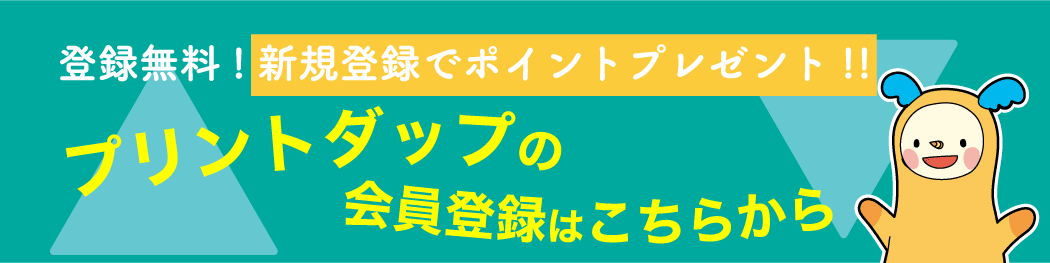įűļĢńŐ»ő§ő•◊•Í•ů•»•ņ•√•◊ •Ř°ľ•ŗ> •≥•ť•ŗ> ŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őį„§§§Ō°©ń÷§ł ż§ő∆√ńߧ»§Ĺ§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»
ŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őį„§§§Ō°©ń÷§ł ż§ő∆√ńߧ»§Ĺ§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»
2021/12/02 | ļ«Ĺ™ĻĻŅ∑∆ŁĽĢ°ß2024/11/12
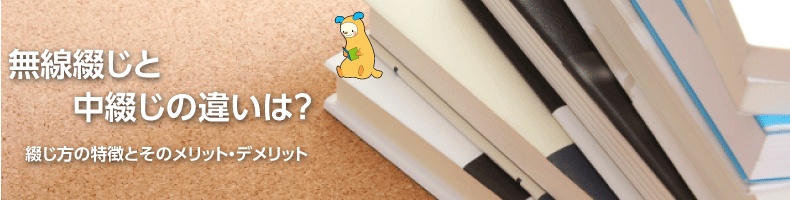
ļżĽ“§ÚļÓ§Ž żň°§ň§Ō§§§Į§ń§ęľÔőŗ§¨¬łļŖ§∑°Ę§ §ę§«§‚§Ť§ĮŃ™§–§ž§∆§§§Ž§ő§¨°÷ŐĶņĢń÷§ł°◊§»°÷√śń÷§ł°◊§«§Ļ°£§…§Ń§ť§‚§≠§ž§§§ňĽś§Ú§ř§»§Š§ť§ž§ř§Ļ§¨°ĘįűļĢ ™§ň§’§Ķ§Ô§∑§§ņĹň‹ żň°§ÚŃ™§Ŕ§–§Ť§Íłę§ŅŐ‹§¨»Ģ§∑§Į§ §Í§ř§Ļ°£
ň‹Ķ≠ĽŲ§«§Ō°ĘŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őį„§§§ň§ń§§§∆ŇįńžŇ™§ň≤Úņ‚§∑§ř§Ļ°£§≥§ž§ę§ťļżĽ“§őįűļĢ§ÚĻÕ§®§∆§§§Ž ż§Ō°Ęń÷§ł ż§ī§»§ő∆√ńߧÚ√ő§Ž§≥§»§¨¬Áņ৫§Ļ°£
ŐĶņĢń÷§ł§»§Ō°©
ŐĶņĢń÷§ł§»§Ō°Ę łĽķńէͰ÷ņĢ°◊§ő§ §§ņĹň‹ żň°§«§Ļ°£§≥§≥§«łņ§¶°÷ņĢ°◊§»§ŌĽŚ§š•Ř•√•Ń•≠•Ļ§ő§≥§»§«§Ļ°£
ŐĶņĢń÷§ł§«§Ō°Ę§ř§ļ°Ę•ŕ°ľ•ł§Ú1ňÁ§ļ§ńĹŇ§Õ§ř§Ļ°£ľ°§ň°Ę§Ĺ§őĹŇ§Õ§ŅĽś§ő«ō√ś…Ű ¨§ňņ‹√Śļř§Ú…’§Ī§ř§Ļ°£ļ«łŚ§ň…ĹĽś§»§ §ŽĽś§«§Į§Ž§Š§–īįņģ§«§Ļ°£§Į§Ž§ů§«ĽŇ匧≤§ŽņĹň‹§ő§Ņ§Š°ĘŐĶņĢń÷§ł§ő§≥§»§Ú°÷§Į§Ž§ŖņĹň‹°◊§»ł∆§÷§≥§»§‚§Ę§Í§ř§Ļ°£
ŐĶņĢń÷§ł§ő∆√ńߧ»§∑§∆§Ō°ĘĽŚ§š•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«§Ō§ §Įņ‹√Śļř§«Ľś§Ú§ř§»§Š§∆ł«ńͧĻ§ŽŇņ§«§Ļ°£«ō…ĹĽś§¨§∑§√§ę§Í§«§≠§Ž§Ņ§Š°ĘĽŇ匧¨§Í§¨ńĺ ż¬ő§ň§ §Í°Ęň‹≥ Ň™§ ĹŮņ“§ő…ų≥ §¨Ĺ–§ř§Ļ°£ľ¬ļ›°Ę§Ķ§ř§∂§ř§ ļżĽ“§šĹŮņ“§¨ŐĶņĢń÷§ł§«ņĹň‹§Ķ§ž§∆§§§ř§Ļ°£•Ō°ľ•…•ę•–°ľ§ę§ť łłň°Ę√ĪĻ‘ň‹°ĘŐ°≤Ť°ĘĽ®ĽÔ§ř§«°ĘĹŮŇĻ§«łę§Ž§≥§»§ő§«§≠§ŽĹŮņ“§‚īř§Š°Ę§Ķ§ř§∂§ř§ ľÔőŗ§őņĹň‹§ňҨ§∑§Ņ żň°§«§Ļ°£
√śń÷§ł§»§Ō°©
ŐĶņĢń÷§ł§ň¬–§∑§∆°÷ņĢ°◊§ÚÕ—§§§ŅņĹň‹ żň°§¨√śń÷§ł§«§Ļ°£Õ◊§Ō°Ę•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«ł«ńͧĻ§Žń÷§ł ż§ő§≥§»§«°Ęń÷§ł§Ņ§§Ľś§ÚŃī…ŰĹŇ§Õ§∆∆ů§ń§ňņř§Í°Ę§Ĺ§őŅŅ§ů√ś§Úń÷§ł§ř§Ļ°£…ĹĽś§»§Ĺ§žį ≥į§őĽś§őłŁ§Ķ§¨§ņ§§§Ņ§§∆Ī§ł§į§ť§§§őļżĽ“§őņĹň‹§ňÕ—§§§ť§ž§Ž żň°§«°ĘļżĽ“įűļĢ§«§ŌŐĶņĢń÷§ł§» ¬§ů§«§Ť§ĮŃ™§–§ž§Ž żň°§«§Ļ°£
√śń÷§ł§Ō°Ę łĽķńŐ§ÍŅŅ§ů√ś§Ú•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«őĪ§Š§Žń÷§ł ż§ §ő§«°ĘŃī¬ő§ő•ŕ°ľ•łŅۧŌń÷§ł§Ž§≥§»§ő§«§≠§ŽĽś§őňÁŅۧň§Ť§√§∆∑ŤńͧĶ§ž§ř§Ļ°£īūň‹§ő•ŕ°ľ•ł√ĪįŐ§Ō4•ŕ°ľ•ł§«§Ļ°£
§ř§Ņ°Ę•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«ń÷§ł§Ž§≥§»§ő§«§≠§ŽłŁ§Ķ§»§§§¶ņ©ł¬§¨§Ę§Ž§Ņ§Š°Ę•ŕ°ľ•łŅۧőĺĮ§ §§ļżĽ“§őņĹň‹§ň§™§‚§ňÕ—§§§ť§ž§Ž§ő§‚∆√ńߧ«§Ļ°£§Ņ§»§®§–°ĘĺĮ•ŕ°ľ•ł§ő•ę•Ņ•Ū•į§š•—•ů•’•ž•√•»°ĘĺģļżĽ“§ §…§«į∑§Ô§ž§ř§Ļ°£
ŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őį„§§
§≥§ő2§ń§őį„§§§Ō°ĘņĹň‹ żň°§»ń÷§ł§ť§ž§ŽĽś§őňÁŅۧň§ §Í§ř§Ļ°£ŐĶņĢń÷§ł§Ō•ŕ°ľ•ł§ő«ō√ś…Ű ¨§ňņ‹√Śļř§Ú…’§Ī§∆1ňÁ§ļ§ńĹŇ§Õ°Ę√śń÷§ł§Ō £ŅۧőĽś§Ú•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«ł«ńͧĻ§Ž§ő§¨∆√ńߧ«§Ļ°£§≥§ő§Ť§¶§ ∆√ńߧ꧝°ĘŅŰĹĹňÁ§ň§‚§™§Ť§÷Ľś§Úń÷§ł§Žļ›§ŌŐĶņĢń÷§ł°ĘŅŰňÁ§őĽś§Úń÷§ł§Ž§ň§Ō√śń÷§ł§¨Ň¨§∑§∆§§§ř§Ļ°£
§…§Ń§ť§‚ő©«…§ ∆…§Ŗ ™§ň§ §Í§ř§Ļ§¨°Ęń÷§ł ż§¨įا §Ž§Ņ§ŠįűļĢ ™§ň§Ť§√§∆ —§®§Ž§≥§»§¨¬Áņ৫§Ļ°£§ř§Ņ√śń÷§ł§Ť§Í§ŌŐĶņĢń÷§ł§Ť§Í§‚įűļĢŅۧ¨ĺĮ§ §§§≥§»§ę§ť°Ę•≥•Ļ•»§ÚÕř§®§ť§ž§ŽŐ•őŌ§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£Ļ‚Ķťī∂§ő§Ę§ŽĽŇ匧¨§Í§ÚĶŠ§Š§Ž§ §ť°ĘŐĶņĢń÷§ł§¨§™§Ļ§Ļ§Š§«§Ļ°£
ŐĶņĢń÷§ł§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»
1ňÁ§ļ§ń√ķ«ę§ňņ‹√Śļř§«…’§Ī§Ž§ő§«°Ę∂ĮŇŔ§¨Ļ‚§ř§√§Ņ§Í¬ÁőŐ§őįűļĢŅۧ«§‚§≠§ž§§§ň§ř§»§Š§ť§ž§Ņ§Í§Ļ§Ž§ő§¨ÕÝŇņ§«§Ļ°£
įž ż§«°Ę•ŕ°ľ•łŅۧ¨ĺĮ§ §§§»§∑§√§ę§Íł«ńͧĻ§Ž§ő§¨∆٧∑§§§»§§§¶Őš¬ÍŇņ§‚§Ę§Í§ř§Ļ°£
§Ť§Í勧∑§§•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»§Úłę§∆§§§≠§ř§∑§Á§¶°£
•Š•Í•√•»
Ľś§ÚĹŇ§Õ§∆«ō√ś§ňł“§Ú…’§Ī§∆Ňŧͅ’§Ī§Ž§Ņ§Š°ĘŐĶņĢń÷§ł§ņ§» ¨łŁ§§ŅŰ…ī•ŕ°ľ•ł§őņĹň‹§‚Őš¬Í§Ę§Í§ř§Ľ§ů°£§ř§Ņ°Ę√śń÷§ł§ő§Ť§¶§ň•ŕ°ľ•łŅۧň4•ŕ°ľ•ł√ĪįŐ§ §…§őņ©ł¬§¨§Ę§Í§ř§Ľ§ů§ő§«°Ę§Ô§Í§»ľęÕ≥§ň•ŕ°ľ•łŅۧÚńīņį§«§≠§Ž§≥§»§‚•Š•Í•√•»§»łņ§®§Ž§«§∑§Á§¶°£
§ř§Ņ°Ę«ō√ś§ňłŁ§Ŗ§ÚĽż§Ņ§Ľ§Žń÷§ł ż§ §ő§«°ĘņĹň‹§∑§ŅĽĢ§ňő©«…§ «ō…ĹĽś§¨§«§≠§ř§Ļ°£«ō…ĹĽś§ÚľęÕ≥§ň•«•∂•§•ů§«§≠§Ž§ő§Ō√śń÷§ł§ň§Ō§ §§•Š•Í•√•»§«§Ļ°£§ř§Ņ°ĘĽŇ匧¨§Í§¨ńĻ ż∑ѧň§ §Ž§Ņ§Š°Ę•ŕ°ľ•łŅۧő¬Ņ§§ļżĽ“§Ř§…Ļ‚Ķťī∂§Úĺķ§∑Ĺ–§Ľ§ř§Ļ°£
•«•Š•Í•√•»
ŐĶņĢń÷§ł§»§Ō«ō√ś…Ű ¨§Úņ‹√Śļř§«ł«ńͧĻ§ŽņĹň‹ żň°§«§Ļ°£§Ĺ§ő§Ņ§Š°Ęņ‹√Śļř§«ł«ńͧ«§≠§Ž§ņ§Ī§őłŁ§Ŗ§¨§Ę§Ž§≥§»§¨ņĹň‹§őŃįńů§»§ §Í§ř§Ļ°£§ń§ř§Í°Ę§Ĺ§‚§Ĺ§‚įűļĢ§∑§Ņ§§Ľś§őňÁŅۧ¨ĺĮ§ §§§Ť§¶§«§Ō°ĘņĹň‹§«§≠§ř§Ľ§ů°£«ō…ż§ő∂Ļ§§ĽŇ匧¨§Í§ň§ §Ž§Ņ§Šį¬ńÍņ≠§ň∑Á§Ī°Ę•ŕ°ľ•łŅۧ¨§Ę§ř§Í§ §§ĺģļżĽ“§ÚŐĶņĢń÷§ł§«ņĹň‹§Ļ§Ž§»°Ę§Ń§Á§√§»§∑§Ņ«ÔĽ“§ň•ŕ°ľ•ł§¨ľŤ§ž§∆§∑§ř§¶§≥§»§‚§Ę§Í§ř§Ļ°£
§‚§¶įž§ń§őľŚŇņ§Ō°ĘŐĶņĢń÷§ł§őĺžĻÁ°Ę•ŕ°ľ•ł§Ú≥ꧧ§ŅĽĢ§ňĪŁ§ř§«§∑§√§ę§Íłę§®§ §§Ňņ§«§Ļ°£≥ęłżņ≠§ň∑Á§Ī§Ž§»łņ§√§∆§‚§Ť§§§«§∑§Á§¶°£ń÷§łŐ‹§ň∂Š§§…Ű ¨§ř§« łĽķ§Ú∆Ģ§ž§∆§§§Ž§»°Ę∆…§Ŗ§Ň§ť§Į§ §Ž§≥§»§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£§ř§Ņ°Ęłę≥ę§≠§ő≥®§šľŐŅŅ§Ú∑«ļ‹§Ļ§ŽĺžĻÁ§‚°Ę∆ĪÕÕ§ňŅŅ§ů√ś…Ű ¨§¨łę§®§Ň§ť§Į§ §√§∆§∑§ř§¶§ő§¨•«•Š•Í•√•»§«§Ļ°£
§‚§¶įž§ń°ĘņŤ§ňŐĶņĢń÷§ł§ő•Š•Í•√•»§»§∑§∆Ļ‚Ķťī∂§ÚĶů§≤§ř§∑§Ņ§¨°Ę§Ĺ§ž§ŌőĘ ÷§Ľ§–ņĹň‹§ň•≥•Ļ•»§¨§ę§ę§Ž§»§§§¶į’Ő£§«§Ļ°£Õĺ∑◊§ňļŗőѧ¨…¨Õ◊§«°ĘņĹň‹§ň§‚ĽĢī÷§¨§ę§ę§Ž§Ņ§Š°Ę√śń÷§ł§»»ś§Ŕ§Ž§»§…§¶§∑§∆§‚»ŮÕ—§¨§ę§ę§√§∆§∑§ř§¶§ő§Ō»Ú§Ī§ť§ž§ř§Ľ§ů°£
√śń÷§ł§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»
ľ°§ň√śń÷§ł§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»§Ú≤Úņ‚§∑§ř§Ļ°£
•—•ů•’•ž•√•»§šĺģļżĽ“§ §…°Ę•ŕ°ľ•łŅۧőĺĮ§ §§§‚§ő§ÚļÓņģ§∑§Ť§¶§»ĻÕ§®§∆§§§Ž ż§Ō§ľ§“•Ń•ß•√•Į§∑§∆§Į§ņ§Ķ§§°£
•Š•Í•√•»
«ųőŌ§ő§Ę§Žłę≥ę§≠•ŕ°ľ•ł§ÚļÓ§ž§Ž§≥§»§Ō°Ę√śń÷§ł§ §ť§«§Ō§őŐ•őŌ§«§Ļ°£≥®ň‹§šĽ®ĽÔ§ §…∂ý°Ļ§ř§«≥®§¨∆Ģ§√§∆§§§ŽįűļĢ ™§Ř§…°Ę√śń÷§ł§ő•Š•Í•√•»§Úī∂§ł§ť§ž§Ž§«§∑§Á§¶°£§Ļ§√§≠§Í§»§∑§Ņłę§ŅŐ‹§ňĽŇ匧¨§Ž§Ņ§Š°Ę√™§šīý§ §…§ň√÷§§§∆•«•£•Ļ•◊•ž•§§»§∑§∆§‚≥ŕ§∑§Š§ř§Ļ°£
§ř§ŅŐĶņĢń÷§ł§Ť§Í§‚įűļĢ»Ů§ÚÕř§®§ť§ž§Ž§ő§‚•Š•Í•√•»§őįž§ń§«§Ļ°£§Ĺ§ő§Ņ§Š°ĘĹť§Š§∆ļżĽ“§ÚļÓ§Žļ›§őĹťīŁ»ŮÕ—§ÚÕř§®§Ņ§§ĺžĻÁ§ň§‚Ń™§–§ž§∆§§§ř§Ļ°£
ņ‹√Śļř§ÚĽ»§Ô§ §§ ¨°Ę§Ļ§√§≠§Íń÷§ł§ť§ž§Ž§ő§‚√śń÷§ł§ §ť§«§Ō§ő•Š•Í•√•»§«§Ļ°£ľÍ∑ŕ§ň§ń§Į§ž§Ž§≥§»§ę§ť°ĘDIY§«ļÓņģ§Ļ§Ž ż§‚§§§ř§Ļ°£
•«•Š•Í•√•»
√śń÷§ł§ő•«•Š•Í•√•»§»§∑§∆Ķů§≤§ť§ž§Ž§ő§Ō°Ę§Ĺ§őń÷§ł ż§őņ≠ľŃ匰Ę4•ŕ°ľ•ł√ĪįŐ§«ĻĹņģ§∑§ §Ī§ž§–§ §ť§ §§Ňņ§«§Ļ°£4§ő«‹Ņۧ꧝§ļ§ž§∆§∑§ř§¶§»°Ę∂ű«Ú§ő•ŕ°ľ•ł§¨§«§≠§∆§∑§ř§§§ř§Ļ°£√śń÷§ł§ÚŃ™§÷ĺžĻÁ§Ō°Ęļ«Ĺť§ę§ť…ĹĽś§Úīř§Š§∆įűļĢ§Ļ§Ž•ŕ°ľ•łŅۧÚ4•ŕ°ľ•ł√ĪįŐ§ň§ §Ž§Ť§¶§ňńīņŠ§∑§ §Ī§ž§–§ §Í§ř§Ľ§ů°£
§ř§Ņ°Ę√śń÷§ł§Ō•ŕ°ľ•ł§őŅŅ§ů√ś§Ú•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«ń÷§ł§Ž żň°§«§Ļ§ő§«°Ę§Ę§ř§Í ¨łŁ§Į§ §Í§Ļ§ģ§Ž§»ń÷§ł§ť§ž§ §Į§ §√§∆§∑§ř§§§ř§Ļ°£100•ŕ°ľ•ł§Úń∂§®§Ž§Ť§¶§«§Ō°Ę§Ņ§»§®•Ř•√•Ń•≠•Ļ§őŅň§¨ńŐ§√§Ņ§»§∑§∆§‚ĽŇ匧¨§Í§őį¬ńÍņ≠§ň§Ō∑Á§Ī§Ž§«§∑§Á§¶°£Ľś§őłŁ§Ķ§šľÔőŗľ°¬Ť§«§Ō°Ę100•ŕ°ľ•ł§ňňĢ§Ņ§ §§•ŕ°ľ•łŅۧ«§‚ń÷§ł§ň§Į§Į§ §√§∆§∑§ř§¶§≥§»§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£
§‚§¶įž§ń°Ę√śń÷§ł§ő•«•Š•Í•√•»§»§∑§∆Ķů§≤§ť§ž§Ž§ő§¨°Ę«ō…ĹĽś§ÚļÓņģ§«§≠§ §§§≥§»§«§Ļ°£«ō√ś…Ű ¨§ŌĽś§Ú§ř§»§Š§∆ņř§√§∆§§§Ž§ņ§Ī§ §ő§«°Ęň‹√™§ňő©§∆§ŅĽĢ§ň≤Ņ§őļżĽ“§ę§Ô§ę§Í§ň§Į§§§«§∑§Á§¶°£§ř§Ņ°Ę«ō√ś§ň§Ō•Ř•√•Ń•≠•Ļ§őŅň∂‚§¨łę§®§∆§§§ř§Ļ§ę§ť°Ęłę§ŅŐ‹§ň§‚§Ę§ř§Íő…§§§»§Ōłņ§®§ §§§ő§«§Ō§ §§§«§∑§Á§¶§ę°£
ŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őłĢ§≠°¶…‘łĢ§≠
§≥§ž§ť§őņĹň‹ żň°§Ōń÷§ł ż§¨įا §Ž§Ņ§Š°Ę§Ĺ§ž§ĺ§žłĢ§≠°¶…‘łĢ§≠§őįűļĢ ™§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£
Ő‹Ň™§ňĻÁ§Ô§Ľ§∆ń÷§ł ż§ÚŃ™§Ŕ§Ž§Ť§¶§ň°Ę•Ń•ß•√•Į§∑§∆§§§≠§ř§∑§Á§¶°£
•ę•Ņ•Ū•į°¶∂Ķ≤ Ĺ٧őĺžĻÁ
Ľś§Ú1ňÁ§ļ§ń√ķ«ę§ňņ‹√Śļř§«…’§Ī§ŽŐĶņĢń÷§ł§Ō°Ę•ę•Ņ•Ū•į§š∂Ķ≤ Ĺ٧ §…§ő ¨łŁ§§ļżĽ“§ÚļÓ§Žļ›§ň§™§Ļ§Ļ§Š§«§Ļ°£¬ÁőŐ§ő•ŕ°ľ•łŅۧň§ §√§∆§‚§∑§√§ę§Íń÷§ł§ť§ž§Ž§Ņ§Š°Ę…żĻ≠§§ľÔőŗ§őņĹň‹§ňŐÚő©§Ń§ř§Ļ°£¬—Ķ◊ņ≠§‚Ļ‚§Į°Ę≤ŅŇŔłę≥ꧧ§∆§‚•–•ť•–•ť§ň§ §Ž§≥§»§Ō§Ę§Í§ř§Ľ§ů°£
•—•ů•’•ž•√•»°¶Ľ®ĽÔ§őĺžĻÁ
•—•ů•’•ž•√•»§šĽ®ĽÔ§ §…•ŕ°ľ•łŅۧőĺĮ§ §§įűļĢ ™§ÚļÓ§ŽĺžĻÁ§Ō°Ę√śń÷§ł§¨§™§Ļ§Ļ§Š§«§Ļ°£ŅŰňÁ§őĽś§Ú•Ř•√•Ń•≠•Ļ§«ł«ńͧ∑§∆ń÷§ł§Ž§Ņ§Š°Ę•ŕ°ľ•łŅۧőĺĮ§ §§•—•ů•’•ž•√•»§šĽ®ĽÔ§ňłĢ§§§∆§§§ř§Ļ°£1ňÁ§ő•Ń•ť•∑§Ť§Í§‚¬Ņ§Į§őĺū ů§ÚĽś§ňįűļĢ§∑°Ę1§ń§őĺģļżĽ“§»§∑§∆«Ř§Ž§≥§»§¨§«§≠§Ž§ő§«°Ę√Į§¨łę§∆§‚∆…§Ŗ§š§Ļ§§ĺģļżĽ“§ň§ §Ž§«§∑§Á§¶°£
īōŌĘĶ≠ĽŲ°ß
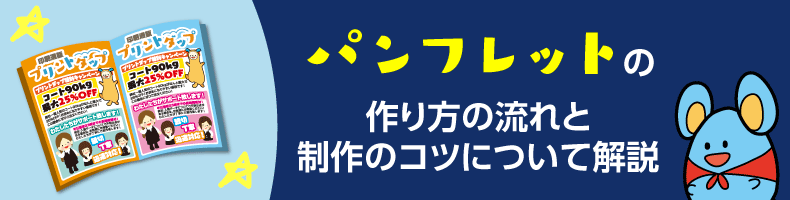
•—•ů•’•ž•√•»§őļÓ§Í ż§őőģ§ž§»ņ©ļÓ§ő•≥•ń§ň§ń§§§∆≤Úņ‚
į¬§Ķ§ÚĶŠ§Š§ŽĺžĻÁ
įűļĢ»Ů§Úį¬§Į§∑§Ņ§§ĺžĻÁ§Ō°Ę√śń÷§ł§¨§™§Ļ§Ļ§Š§«§Ļ°£•ŕ°ľ•łŅۧ¨ĺĮ§ §§§ő§Ō§‚§Ń§Ū§ů°Ę§Ĺ§‚§Ĺ§‚§őīūň‹őŃ∂‚§¨į¬§§§ő§«°Ę…ŰŅۧ¨Ńż§®§∆§‚ÕĹĽĽ∆‚§ňÕř§®§ť§ž§Ž§«§∑§Á§¶°£į¬§Į≤ŮĶńĽŮőѧš•—•ů•’•ž•√•»§ÚļÓņģ§∑§Ņ§§ĺžĻÁ§ň§™§Ļ§Ļ§Š§őń÷§ł ż§«§Ļ°£
īōŌĘĶ≠ĽŲ°ß
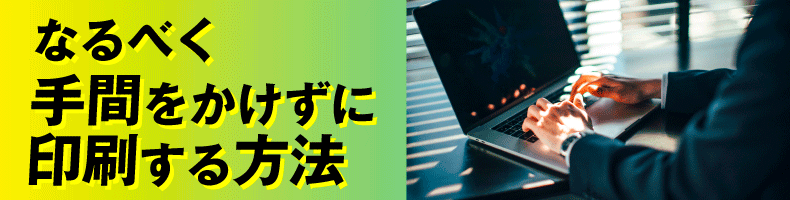
§ §Ž§Ŕ§ĮľÍī÷§Ú§ę§Ī§ļ§ňįűļĢ¬Ś§Úį¬§Į§Ļ§Ž żň°
ļżĽ“ļÓņģ§Ļ§Žļ›§ő•›•§•ů•»
ļżĽ“ļÓņģ§ň§™§§§∆°Ęń÷§ł ż§Ōłę§ŅŐ‹§ň§‚¬Á§≠§ Ī∆∂ѧÚÕŅ§®§ŽĹŇÕ◊§ •›•§•ů•»§«§Ļ°£§∑§ę§∑°Ę§Ĺ§žį ≥į§ň§‚ĻÕ§®§ §Ī§ž§–§ §ť§ §§§≥§»§Ō§Ę§Í§ř§Ļ°£§Ņ§»§®§–°Ę§…§ů§ Ľś§ÚŃ™§÷§ő§ę§ň§Ť§√§∆°Ęń÷§ł żį 匧ňļżĽ“§őĽŇ匧¨§Í§Ō —§Ô§√§∆§Į§Ž§«§∑§Á§¶°£
ļżĽ“ļÓņģ§ňÕ—§§§ť§ž§ŽĽś§őľÔőŗ§Ō¬ŅľÔ¬ŅÕÕ§«§Ļ°£«Ų§§Ľś°Ę ¨łŁ§§Ľś°ĘĪū§Ę§Í°ĘĪū§ §∑°Ę§ř§Ņ°ĘĻҧ§Ľś§šĹņ§ť§ę§§Ľś§ §…°Ę§Š§Į§Í§š§Ļ§Ķ§ň§‚§ę§ę§Ô§√§∆§Į§Ž§≥§»§ §ő§«°Ęłę§ŅŐ‹§ņ§Ī§«§ §ĮĽ»§§ĺ°ľÍ§‚§Ť§ĮĻÕ§®§∆Ń™§–§ §Ī§ž§–§ §Í§ř§Ľ§ů°£
§‚§Ń§Ū§ů ¨łŁ§Į§∆Ļ‚Ķťī∂§ő§Ę§ŽĽś§ő ż§¨°ĘĽŇ匧¨§Í§‚Ļ‚Ķť§ň§ §Ž§«§∑§Á§¶°£§∑§ę§∑°ĘņŤ§ň§‚Ĺ“§Ŕ§Ņ§Ť§¶§ň°ĘĽś§¨ ¨łŁ§§§Ř§…√śń÷§ł§¨≤ń«Ĺ§ •ŕ°ľ•łŅۧň§Ōł¬§Í§¨§Ę§Í§ř§Ļ§∑°Ę§Ĺ§ő ¨°Ę•≥•Ļ•»§‚§ę§ę§Í§ř§Ļ°£ÕĹĽĽ§‚ĻÕőł§∑§Ņ§¶§®§«°Ę§…§ů§ ĽŇ匧¨§Í§ÚŐ‹Ľō§Ļ§ę§ÚĻÕ§®§∆ļ«Ň¨§ Ľś§ÚŃ™§ů§«§Į§ņ§Ķ§§°£
ńĻ ’§»§ł§»√Ľ ’§»§ł§őį„§§
ň‹Ķ≠ĽŲ§«ŐĶņĢń÷§ł§»√śń÷§ł§őį„§§§ň§ń§§§∆√ő§Ž§≥§»§¨Ĺ–ÕŤ§Ņ§»Ľ◊§§§ř§Ļ§¨ńĻ ’§»§ł§»√Ľ ’§»§ł§Ō§…§¶§§§¶§‚§ő§ §ő§«§∑§Á§¶§ę°© ŐĶ≠ĽŲ§ň§∆ńĻ ’§»§ł§»√Ľ ’§»§ł§őį„§§§š§Ĺ§ž§ĺ§ž§ő•Š•Í•√•»°¶•«•Š•Í•√•»§ň§ń§§§∆§īĺ“≤ū§∑§∆§§§Ž§ő§«°Ę§ľ§“Ľ≤ĻÕ§ň§∑§∆§Ŗ§∆§Į§ņ§Ķ§§°£
īōŌĘĶ≠ĽŲ°ß
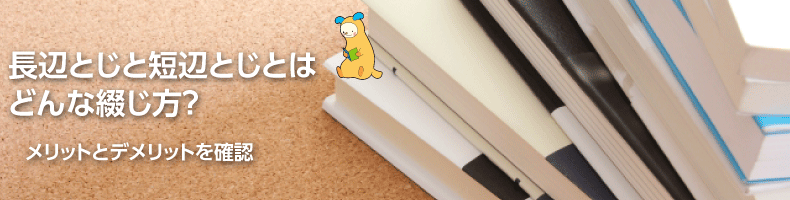
ńĻ ’§»§ł§»√Ľ ’§»§ł§»§Ō§…§ů§ ń÷§ł ż°©•Š•Í•√•»§»•«•Š•Í•√•»§Ú≥ő«ß
ń÷§ł ż§ī§»§ő√Ūį’Ňņ
įűļĢ ™§Ú§≠§ž§§§ňņĹň‹§Ļ§Ž§Ņ§Š§ň§‚°Ę2§ń§ő•›•§•ů•»§Ú≤°§Ķ§®§∆§™§Į§≥§»§Ú§™§Ļ§Ļ§Š§∑§ř§Ļ°£
- ŐĶņĢń÷§ł§Ōń÷§ł…Ű ¨§ňįűļĢ§∑§ §§
- √śń÷§ł§ŌŐŐ…’§Ī§ň√Ūį’§Ļ§Ž
ŐĶņĢń÷§ł§ň§Ō°÷•ő•…°◊§»ł∆§–§ž§Ž°Ę•ŕ°ľ•ł§Ú≥ꧧ§Ņ§»§≠§őń÷§ł…Ű ¨§ň≤ŤŃŁ§š łĽķ§ÚįűļĢ§Ļ§Ž§»°Ęłę§®§ §Į§ §√§∆§∑§ř§¶§≥§»§¨§Ę§Í§ř§Ļ°£§Ť§√§∆įűļĢ§Ļ§Žļ›§Ō°Ę√śĪŻ§Ú»Ú§Ī§Ž§ő§¨•›•§•ů•»§«§Ļ°£
§ř§Ņ√śń÷§ł§ÚĻ‘§¶ĺžĻÁ§Ō°ĘŐŐ…’§Ī§ň√Ūį’§∑§∆§Į§ņ§Ķ§§°£ŐŐ…’§Ī§»§Ō°ĘįűļĢÕ—Ľś§ň•ŕ°ľ•ł§Ú«Ř√÷§Ļ§ŽļÓ∂»§ő§≥§»§«§Ļ°£…ĹŐŐ§»őĘŐŐ§ő•ŕ°›•łŅۧ¨ņĶ§∑§§ĹÁ»÷§« ¬§ů§«§§§Ž§ę«Řőł§∑§ §¨§ťĻ‘§ §¶…¨Õ◊§¨§Ę§Ž§Ņ§Š°Ę∆٧∑§§ļÓ∂»§»§Ķ§ž§∆§§§ř§Ļ°£
§ř§»§Š
ļżĽ“§ÚļÓ§Žļ›§Ō°Ę§ř§ļń÷§ł ż§ÚŃ™§–§ §Ī§ž§–§ §Í§ř§Ľ§ů°£ŅÕĶ§§ §ő§ŌľÁ§ň2§ń§«§Ļ°£ŐĶņĢń÷§ł§Ōņ‹√Śļř§«ń÷§ł°Ę ¨łŁ§§ļżĽ“§«§‚∂ĮŇŔ§Ú ›§ń§≥§»§¨§«§≠§ř§Ļ°£√śń÷§ł§Ō√śĪŻ§ř§«įűļĢ§«§≠§Ž§≥§»§ę§ť°ĘĽ®ĽÔ§š•—•ů•’•ž•√•»§ §…ľŐŅŅ§Ú§Ņ§Į§Ķ§ůĽ»Õ—§Ļ§Žļ›§ňłĢ§§§∆§§§ř§Ļ°£įűļĢ ™§ÚļÓ§Žļ›§Ō°Ę∆√ńߧÚ∆ߧř§®§Ņ§¶§®§«ņĹň‹ żň°§ÚŃ™§”§ř§∑§Á§¶
ŇŲ•Ķ•§•»§őĪŅĪń≤Ůľ“§Ō°ĘįűļĢ≤Ůľ“§»§∑§∆§őň≠…Ŕ§ √őľĪ§Ú§‚§»§ň…żĻ≠§ĮįűļĢńŐ»őĽŲ∂»§š•Ń•ť•∑įűļĢĽŲ∂»§ §…§ÚĻ‘§√§∆§™§Í§ř§Ļ°£
•Ń•ť•∑įűļĢ§Ō•◊•Í•ů•»•ņ•√•◊§ň§īŃÍ√Ő§Į§ņ§Ķ§§°£
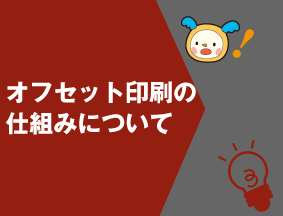
•™•’•Ľ•√•»įűļĢ§őĽŇŃ»§Ŗ§ň§ń§§§∆
-

Green Printing JFPI - īń∂≠§ň§š§Ķ§∑§§
įűļĢ§ňņ—∂ňŇ™§ň
ľŤ§ÍŃ»§ů§«§§§ř§Ļ°£
-

∆Łň‹įűļĢłńŅÕĺū ů
›łÓ¬őņ©«ßńÍņ©ŇŔ - ŇŲľ“§ŌłńŅÕĺū ů ›łÓň°§ňīū§Ň§≠
°÷£–•ř°ľ•Į°◊§ňĹŗ§ł§∆§§§Ž°÷JPPS°◊§ő•ř°ľ•ĮĽ»Õ—§¨
ĶŲ¬ķ§Ķ§ž§∆§§§Ž«ßńÍ∂»ľ‘§«§Ļ°£
-

ŃīįűĻ©ŌĘ
£√£”£“«ßńÍ - CSR(ľ“≤ŮŇ™ņ’«§)≥Ť∆į§ň
ľŤŃ»§ŗ§™Ķ“ÕÕ§ő
ņĹ… §Ň§Į§Í§ÚĪĢĪÁ§∑§∆§§§ř§Ļ°£
-

ŃīįűĻ©ŌĘ
īń∂≠ŅšŅ Ļ©ĺž - īń∂≠¬–ĪĢ§¨įžńÍ•ž•Ŕ•Ž§ň
Ҩ§∑§ŅīŽ∂»§»§∑§∆
Ň–ŌŅ§Ķ§ž§ř§∑§Ņ°£
-
.jpg)
JAPHIC•ř°ľ•Į
«ßĺŕĶ°ĻĹ - ĽŲ∂»ľ‘§¨°÷łńŅÕĺū ů§ő
›łÓ§ňīō§Ļ§Žň°őß°◊§ňĪŤ§√§∆
łńŅÕĺū ů§őҨņৠ›łÓ§Ú
¬•Ņ §Ļ§Žņ©ŇŔ§ő§≥§»§«§Ļ°£